イタチの侵入を防ぐ家屋メンテナンスは?【定期点検が重要】予防的な対策で、将来の被害を大幅に減らせる

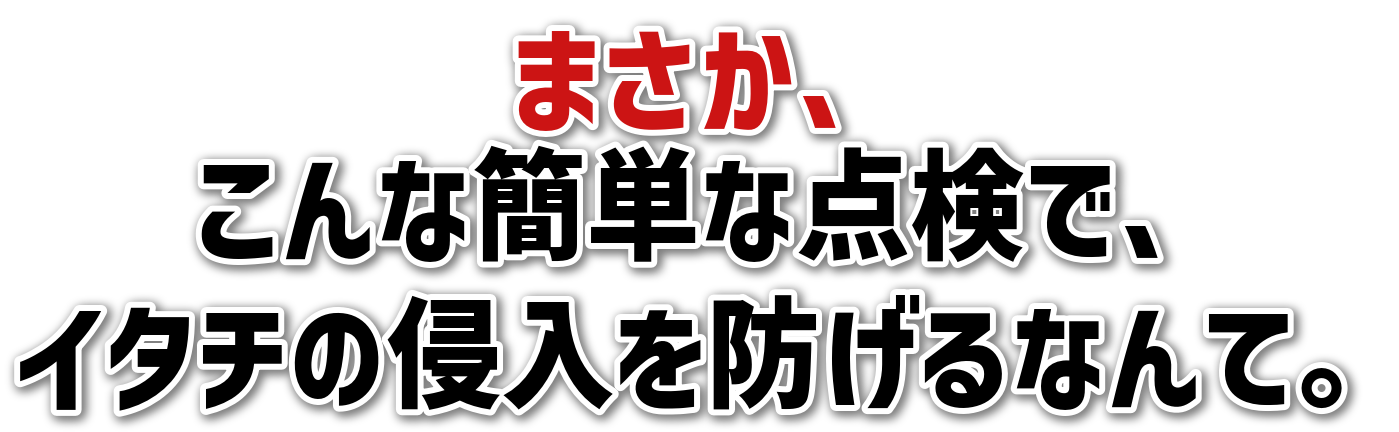
【この記事に書かれてあること】
イタチの侵入で悩んでいませんか?- イタチが侵入しやすい家屋の隙間を徹底チェック
- 効果的な家屋メンテナンスの頻度と方法を比較
- DIYで実践できるイタチ撃退テクニック
- 見落としがちなイタチ被害の前兆と対処法
- 季節別のイタチ対策ポイントを解説
家屋メンテナンスが重要な鍵を握っています。
でも、「どこをチェックすればいいの?」「どのくらいの頻度で点検すべき?」と疑問が湧くかもしれません。
本記事では、イタチ対策の要となる家屋メンテナンスの秘訣を徹底解説します。
定期点検の重要性から、DIYで実践できる驚きの対策術まで、あなたの家を守る具体的な方法をお教えします。
これを読めば、イタチフリーの安心な住まいづくりが始められますよ。
さあ、一緒にイタチ撃退作戦を始めましょう!
【もくじ】
イタチの侵入を許す家屋の隙間とは?今すぐ確認を

イタチが侵入しやすい「5つの要注意箇所」を徹底解説!
イタチの侵入を防ぐには、家の5つの要注意箇所を知ることが大切です。さっそく、イタチが忍び込みやすい場所を見ていきましょう。
まず1つ目は屋根裏です。
「えっ、屋根裏にイタチが?」と驚くかもしれません。
でも、イタチは木登りが得意。
屋根裏は暖かくて静かなので、イタチにとっては天国のような場所なんです。
2つ目は軒下。
軒下の隙間からスルスルっと侵入してしまうことも。
「うちの軒下、大丈夫かな…」と心配になってきますよね。
3つ目は外壁の隙間。
古い家屋だと、外壁にヒビが入っていることも。
イタチはその小さな隙間をみつけて、「よいしょ」っと家の中に入り込んでしまうんです。
4つ目は換気口。
新鮮な空気を取り込むための大切な場所ですが、イタチにとっては格好の侵入口に。
「換気口、覚えておかなきゃ」ですね。
最後は配管周り。
水道管やガス管が通っている場所は、意外と隙間があるもの。
イタチはその隙間を見逃しません。
これら5つの場所を覚えておけば、イタチ対策の第一歩が踏み出せます。
「よし、今日から家のチェックだ!」という気持ちになりませんか?
定期的に点検することで、イタチの侵入を未然に防げるんです。
家族みんなで協力して、イタチ対策を始めましょう。
イタチ被害の前兆!「家屋の劣化サイン」を見逃すな
イタチの侵入を防ぐには、家の劣化サインを見逃さないことが重要です。早めに気づけば、被害を防げる可能性が高くなります。
では、どんなサインに注目すればいいのでしょうか。
まず、外壁の亀裂に気をつけましょう。
小さな亀裂でも、イタチには十分な侵入口になってしまいます。
「えっ、こんな小さな隙間から入れるの?」と思うかもしれませんが、イタチは驚くほど細い隙間から侵入できるんです。
次に注目したいのは軒下の隙間拡大。
軒下の板と壁の間に隙間ができると、イタチの格好の侵入口に。
「うちの軒下、ちょっと隙間が気になるな…」という方は要注意です。
屋根材のめくれも見逃せません。
台風や強風で屋根材がめくれると、そこからイタチが侵入することも。
「屋根、大丈夫かな?」と不安になったら、プロに点検を依頼するのも良いでしょう。
他にも注意したい劣化サインがあります。
- 木材の腐食
- 金属部分の錆び
- 窓枠や戸袋のゆがみ
- 基礎のひび割れ
「家のメンテナンス、意外と大切なんだな」と実感できるはずです。
定期的に家の外回りをチェックする習慣をつけましょう。
家族みんなで「イタチ探偵団」になって、劣化サインを探すのも楽しいかもしれません。
家を守ることは、家族の安全を守ることにもつながるんです。
イタチの侵入跡を見分けるポイント「3つの痕跡」に注目
イタチが家に侵入したかどうかを知るには、特徴的な痕跡を見つけることが大切です。ここでは、イタチの侵入跡を見分けるポイントとなる「3つの痕跡」について詳しく解説します。
まず1つ目は、小さな穴です。
イタチは体が細長いため、直径5ミリ程度の小さな穴からでも侵入できてしまいます。
「えっ、そんな小さな穴から入れるの?」と驚くかもしれませんが、イタチの体の柔軟性は想像以上なんです。
家の外壁や軒下、基礎部分などをよく観察してみましょう。
2つ目は、爪痕です。
イタチは鋭い爪を持っており、侵入する際に壁や木材に爪痕を残すことがあります。
この爪痕は通常、縦に平行な線が4〜5本並んだ形になります。
「うちの壁にも似たような跡があるかも…」と思ったら、要注意です。
3つ目は、毛や糞の痕跡です。
イタチが通った場所には、体毛や糞が残されていることがあります。
イタチの毛は短くて細く、茶色や灰色をしています。
糞は細長く、ねじれた形状が特徴的です。
「何か変な物が落ちてる…」と思ったら、イタチの痕跡かもしれません。
これらの痕跡を見つけるコツは、以下の3点です。
- 定期的に家の周りを丁寧にチェックする
- 懐中電灯を使って暗い場所も細かく調べる
- 気になる場所は写真を撮って記録する
もし、これらの痕跡を見つけたら、すぐに対策を講じることが大切です。
早めの発見と対応が、イタチ被害を最小限に抑える鍵となるんです。
家族みんなで協力して、イタチフリーの快適な住まいを守りましょう。
定期点検で見落としがちな「意外な侵入経路」とは?
イタチの侵入を防ぐには、普段の点検では見落としがちな「意外な侵入経路」にも注目する必要があります。ここでは、そんな意外な侵入経路について詳しく解説します。
まず挙げられるのが、雨どいです。
「えっ、雨どいから?」と驚くかもしれませんが、イタチは雨どいを使って屋根まで登ることができるんです。
特に、壁に近接した雨どいは要注意。
イタチにとっては便利な「はしご」になってしまいます。
次に注目したいのは、樹木の枝です。
家の近くに生えている木の枝が、屋根や窓に接している場合、イタチはその枝を伝って家に侵入することがあります。
「庭木が侵入経路になるなんて…」と意外に思うかもしれませんね。
物置や倉庫も意外な侵入経路になり得ます。
家屋本体とは別に建てられた物置や倉庫に、まずイタチが住み着き、そこから本体への侵入を試みることがあるんです。
「物置、最近チェックしてないな…」という方は要注意です。
他にも、以下のような意外な侵入経路があります。
- エアコンの室外機周り
- ポストの裏側
- ドアや窓の weatherstrip(すきま風防止用のゴム)の隙間
- foundation vent(基礎部分の換気口)
「へえ、こんなところからも入れるんだ」と新たな発見があるはずです。
定期点検の際は、家の周りをぐるっと一周して、これらの意外な侵入経路もチェックしてみましょう。
家族みんなで「イタチ侵入経路探しゲーム」として楽しむのも良いかもしれません。
早めの発見と対策が、イタチ被害を防ぐ最大の武器です。
意外な侵入経路にも目を光らせて、イタチフリーの快適な住まいを守りましょう。
「よし、今日から家の隅々までチェックだ!」という気持ちで、家族みんなでイタチ対策に取り組んでみてはいかがでしょうか。
イタチ対策はダメ!「やってはいけない5つの行動」
イタチ対策には、逆効果になってしまう行動があります。ここでは、絶対にやってはいけない5つの行動について詳しく解説します。
これらを避けることで、より効果的なイタチ対策ができるようになりますよ。
まず1つ目は、殺虫剤の使用です。
「イタチを見つけたら殺虫剤でやっつけよう!」と思うかもしれませんが、これは大変危険。
イタチは哺乳類なので、殺虫剤は効果がありません。
それどころか、毒性のある薬品を家屋内で使うことで、人体に悪影響を及ぼす可能性があるんです。
2つ目は、侵入口をすぐに塞ぐこと。
「穴を見つけたらすぐに塞げばいいんでしょ?」と思いがちですが、これも要注意。
イタチが中にいる可能性があるからです。
閉じ込められたイタチは、パニックになって家の中を荒らす可能性があります。
3つ目は、食べ物を置いて誘き寄せること。
「食べ物で釣って捕まえよう」という作戦は逆効果。
イタチを引き寄せるだけでなく、他の害獣まで呼び寄せてしまう可能性があります。
4つ目は、大音量の音楽を流すこと。
「うるさい音で追い払おう」と考えるかもしれませんが、これも効果は薄いです。
イタチは意外と騒音に強く、むしろストレスで攻撃的になる可能性があります。
最後は、自分で捕獲しようとすること。
「よし、自分で捕まえてやる!」と意気込むのはとても危険です。
イタチは驚くと攻撃的になることがあり、噛まれる可能性もあります。
これらの行動を避けるべき理由をまとめると:
- 人体や環境に悪影響を及ぼす可能性がある
- イタチを閉じ込めてしまう危険性がある
- 他の害獣も引き寄せてしまう
- イタチをより攻撃的にしてしまう
- 自分自身がケガをする危険性がある
大切なのは、冷静に状況を把握し、適切な対策を講じることです。
専門家のアドバイスを受けるのも良い選択肢です。
イタチ対策は、正しい知識と適切な方法で行うことが大切。
「よし、しっかり勉強して賢く対策しよう!」という気持ちで、家族みんなで協力してイタチ問題に取り組んでいきましょう。
家屋メンテナンスの重要性と効果的な方法を比較

外壁vs屋根!イタチ対策に効く「メンテナンス頻度」の違い
イタチ対策には、外壁と屋根のメンテナンス頻度が異なります。外壁は年1回、屋根は2〜3年に1回の点検が効果的です。
「えっ、外壁の方が頻繁に点検が必要なの?」と思われるかもしれませんね。
実は、イタチは外壁の小さな隙間からも侵入できてしまうんです。
外壁は日々の風雨にさらされているため、劣化が早く進みやすいんです。
外壁のメンテナンスでは、特に以下の点に注意しましょう。
- ヒビや亀裂がないか
- 塗装の剥がれはないか
- 木部の腐りはないか
- 金属部分の錆びはないか
もし空洞音がしたら、中が傷んでいる可能性があります。
一方、屋根は比較的頑丈ですが、台風や大雨の後には要注意。
「屋根裏に雨漏りの跡があったぞ」なんて気づいた時には、もうイタチの住処になっているかもしれません。
屋根の点検では、特に以下の点をチェックしましょう。
- 瓦のずれや割れ
- 軒先や谷部分の腐食
- 換気口の網の破れ
そんな時は双眼鏡を使って地上から観察するのもひとつの手です。
不安な箇所があれば、専門家に相談するのが賢明です。
定期的なメンテナンスを行うことで、イタチの侵入を防ぐだけでなく、家の寿命も延びるんです。
「一石二鳥だね!」というわけです。
家族みんなで協力して、快適な住まいを守りましょう。
木造住宅vs鉄筋コンクリート造「イタチ侵入リスク」を比較
木造住宅と鉄筋コンクリート造では、イタチの侵入リスクに大きな違いがあります。木造住宅の方が侵入リスクが高く、より頻繁なメンテナンスが必要です。
「えっ、木造住宅の方がイタチに狙われやすいの?」と驚く方も多いかもしれません。
実は、木造住宅には以下のような特徴があるんです。
- 木材の隙間からイタチが侵入しやすい
- 経年劣化で隙間が広がりやすい
- イタチが好む温かみのある環境
特に気をつけたいのが、軒下や外壁の継ぎ目部分。
「ここから入られたらたまらないな」と思う箇所は、重点的にチェックしましょう。
一方、鉄筋コンクリート造は比較的イタチに強い構造です。
でも、油断は禁物!
以下のような箇所には注意が必要です。
- 換気口やダクト周り
- 配管の貫通部分
- 外壁のひび割れ
「コンクリートなら大丈夫だろう」という油断が、イタチを招き入れる結果になるかもしれません。
どちらの構造でも、定期的なメンテナンスが鍵となります。
「ガタガタ」「キーキー」といった異音や、「何か臭うな」という異臭に気づいたら要注意。
早めの対処が、大きな被害を防ぐコツなんです。
家は私たちの大切な城。
木造でも鉄筋コンクリートでも、イタチから守るためにこまめなチェックを心がけましょう。
「よし、明日から我が家の点検だ!」という気持ちで、イタチ対策を始めてみませんか?
新築vs築年数の経った家「メンテナンス頻度」はどう違う?
新築と築年数の経った家では、メンテナンス頻度に大きな違いがあります。新築は年1回程度、築年数の経った家は3か月ごとの点検が望ましいんです。
「えっ、そんなに違うの?」と驚く方も多いかもしれませんね。
実は、家は年を重ねるごとに、イタチに狙われやすくなってしまうんです。
新築の場合、建材がピカピカで隙間も少ないため、イタチも侵入しにくいんです。
でも、油断は禁物!
以下のような箇所は、新築でもしっかりチェックしましょう。
- 換気口の周り
- 屋根と外壁の接合部
- 配管の貫通部分
新築だからといって安心せず、定期的な点検を心がけましょう。
一方、築年数の経った家は要注意です。
経年劣化によって、以下のような問題が起きやすくなります。
- 外壁のヒビや剥がれ
- 屋根材のずれや劣化
- 木部の腐食や虫食い
- 基礎部分のひび割れ
「うちの家、大丈夫かな…」と不安になった方は、今すぐ点検を始めましょう。
築年数の経った家では、3か月ごとの点検がおすすめです。
「えっ、そんなに頻繁に?」と思うかもしれません。
でも、小まめな点検こそが、大きな被害を防ぐ秘訣なんです。
点検の際は、家族総出で「イタチ探偵団」になるのも楽しいかもしれませんね。
「あれ?ここにヒビが…」「この臭い、ちょっと怪しいぞ」なんて会話をしながら、家中をくまなくチェック。
それが、イタチ対策の第一歩になるんです。
新築も築古も、大切な我が家。
イタチから守るため、適切なメンテナンスを心がけましょう。
「よし、今日から定期点検を習慣にしよう!」そんな気持ちで、家族みんなでイタチ対策に取り組んでみませんか?
DIY補修vs業者依頼「イタチ対策の費用対効果」を徹底比較
イタチ対策の補修方法には、DIYと業者依頼の2つの選択肢があります。小規模な補修ならDIY、大規模や高所作業は業者依頼が費用対効果に優れています。
「えっ、自分でもイタチ対策できるの?」と思う方も多いかもしれませんね。
実は、簡単なDIY補修で防げる侵入口もたくさんあるんです。
DIYで効果的な対策には、以下のようなものがあります。
- 小さな隙間のコーキング処理
- 換気口への金網の取り付け
- 軒下や外壁の簡単な補修
「よし、やってみよう!」という方は、安全に気をつけて挑戦してみてください。
一方、業者依頼が必要なケースもあります。
例えば、以下のような場合です。
- 屋根や高所の作業
- 大規模な外壁補修
- 家屋内での繁殖が疑われる場合
DIYのメリットは、コストが抑えられる点。
でも、「ちょっと自信ないなぁ」という難しい作業は、むしろ業者依頼の方が長期的には安くつくかもしれません。
業者依頼のメリットは、確実な対策が期待できる点。
特に、イタチが家屋内で繁殖している疑いがある場合は、専門知識を持つ業者に任せるのが賢明です。
費用面では、DIYなら数千円から数万円、業者依頼なら数万円から数十万円程度が目安。
「えっ、そんなにかかるの?」と驚く金額かもしれません。
でも、イタチ被害を放置すると、家の損傷が進み、最終的には数百万円単位の修繕が必要になることも。
結局のところ、小さな対策は自分で、大きな問題は業者にお任せ。
これが、費用対効果の高いイタチ対策の鉄則なんです。
「よし、できることから始めよう!」そんな気持ちで、イタチとの戦いに挑んでみませんか?
春夏秋冬で変わる!「季節別イタチ対策」のポイント
イタチ対策は季節によって変わります。春は繁殖期、夏は子育て期、秋は食料確保期、冬は越冬期と、各季節に合わせた対策が効果的です。
「えっ、季節によって対策を変えなきゃいけないの?」と驚く方も多いかもしれません。
でも、イタチの生態を知れば、より効果的な対策ができるんです。
まず、春の対策。
この季節はイタチの繁殖期です。
以下のポイントに注意しましょう。
- 屋根裏や壁の隙間を徹底チェック
- 庭の整理整頓で隠れ場所をなくす
- 強い香りの植物(ラベンダーなど)を植える
繁殖のための巣作りが始まっているかもしれません。
夏の対策は、子育て中のイタチに注意。
この時期は特に警戒心が強くなります。
- 餌となる小動物を寄せ付けない環境作り
- 夜間の物音に注意(子イタチの鳴き声)
- 換気口や通気口の点検強化
秋の対策は、越冬準備を始めるイタチに備えましょう。
- 落ち葉の清掃で隠れ場所をなくす
- 果樹の実の早めの収穫
- コンポストの管理を徹底
冬の対策は、暖かい場所を求めるイタチに注意。
- 屋根裏や壁の断熱材のチェック
- 暖房設備周りの点検
- 雪で隠れた侵入口の確認
季節に合わせた対策で、一年中イタチを寄せ付けない家づくりができます。
「よし、カレンダーに対策の予定を書き込もう!」そんな気持ちで、計画的なイタチ対策を始めてみませんか?
家族みんなで協力して、快適な住まいを守りましょう。
イタチ撃退!驚きの家屋メンテナンス術5選

新聞紙活用法!「イタチの通り道」を簡単発見
イタチの通り道を見つけるのに、新聞紙が大活躍します。古新聞を丸めて侵入口に詰めると、イタチが通った跡がすぐに分かるんです。
「えっ、新聞紙でイタチの通り道が分かるの?」と思われるかもしれませんね。
実は、この方法がとても効果的なんです。
やり方は簡単!
- 古新聞を丸めて、棒状にする
- イタチが侵入しそうな隙間に詰める
- 翌日、新聞紙を確認する
「ガサガサ」という音がしたら、イタチが通っている証拠かもしれません。
この方法のいいところは、安全で手軽なこと。
イタチに危害を加えることなく、侵入経路を特定できるんです。
注意点は、新聞紙を詰める場所。
換気口や重要な通気口は避けましょう。
「うっかり家の中が蒸し暑くなっちゃった」なんてことにならないよう気をつけてください。
また、この方法は短期的な対策です。
イタチの通り道を見つけたら、次は本格的な対策を立てる必要があります。
「よし、見つけたぞ!」という喜びもつかの間、すぐに次の対策を考えましょう。
家族みんなで「イタチ探偵団」になって、新聞紙チェックを楽しむのもいいかもしれません。
「あっ!ここの新聞紙、動いてる!」なんて声が上がれば、イタチ対策の第一歩は成功です。
新聞紙一枚で、イタチの秘密を暴く。
simple is best、というわけです。
さあ、古新聞を集めて、イタチとの知恵比べを始めましょう!
猫砂パワー!「イタチを寄せ付けない」匂い対策術
イタチを寄せ付けない強力な武器、それが使用済みの猫砂です。イタチは猫を天敵と認識するため、猫の匂いがする場所を避ける習性があるんです。
「えっ、使用済みの猫砂?ちょっと臭くない?」と思われるかもしれません。
でも、この方法はとても効果的なんです。
やり方を見てみましょう。
- 使用済みの猫砂を準備する(友人や知人から分けてもらうのもアリ)
- 小さな布袋や網袋に入れる
- イタチの侵入経路や出没場所に置く
イタチは鼻が敏感なので、猫の匂いを嗅ぐだけで「ここは危険だ!」と感じて近づかなくなるんです。
注意点としては、猫砂を直接撒くのは避けること。
袋に入れることで、風で飛んだり雨で流れたりするのを防げます。
「庭中が猫砂だらけ」なんて事態は避けたいですよね。
また、定期的に交換するのも大切。
「匂いが薄くなってきたかな?」と思ったら、新しい猫砂に交換しましょう。
2週間に1回程度の交換がおすすめです。
この方法の良いところは、安全で自然なこと。
化学物質を使わないので、人やペットにも優しいんです。
「エコなイタチ対策だね!」というわけ。
ただし、猫アレルギーの方は使用を控えましょう。
「くしゅん!イタチは追い払えたけど、今度は鼻水が止まらない」なんてことになっては本末転倒です。
家族みんなで「どこに置こうかな?」と相談しながら、猫砂作戦を実行するのも楽しいかもしれません。
イタチ対策が、思わぬ家族の絆づくりになるかも。
猫砂パワーで、イタチを撃退。
自然の力を借りた、賢い対策術なんです。
さあ、猫砂を準備して、イタチフリーの家づくりを始めましょう!
ペットボトルで作る!「イタチ撃退ライト」の設置方法
ペットボトルを使って、簡単にイタチ撃退ライトが作れるんです。反射光でイタチを威嚇する、エコでお手軽な対策方法です。
「えっ、ペットボトルでイタチが撃退できるの?」と驚く方も多いかもしれません。
でも、これがなかなか効果的なんです。
作り方と設置方法を見てみましょう。
- 透明なペットボトルを用意する
- 中に水を入れる
- 庭や侵入経路付近の日当たりの良い場所に置く
水の入ったペットボトルが太陽光を反射して、キラキラと光るんです。
この不規則な光の動きがイタチを驚かせ、近づきにくくするんです。
「ピカピカ光る庭になっちゃうけど、大丈夫?」と心配する方もいるかもしれません。
でも、イタチ対策としては十分効果的。
しかも、見た目もなんだかオシャレ。
「エコな庭の装飾」と思えば、一石二鳥ですよね。
注意点としては、定期的に水を交換すること。
「緑色の水になっちゃった!」なんてことにならないよう、2週間に1回程度の水交換がおすすめです。
この方法の良いところは、コストがほとんどかからないこと。
使い終わったペットボトルを再利用できるので、とってもエコ。
「もったいない精神」にぴったりの対策方法です。
ただし、強風の日は飛ばされないよう気をつけましょう。
「ペットボトルが空中飛行!」なんて事態は避けたいですよね。
必要に応じて、紐で固定するのもいいでしょう。
家族みんなで「どこに置こうかな?」「この角度がいいんじゃない?」なんて話し合いながら設置するのも楽しいかもしれません。
イタチ対策が、家族の協力プロジェクトに変身!
ペットボトル一本で、イタチを撃退。
簡単、エコ、そして意外と効果的。
さあ、今すぐペットボトルを探して、イタチ撃退ライトづくりを始めましょう!
風鈴の意外な使い方!「音でイタチを追い払う」テクニック
風鈴の涼しげな音色が、実はイタチ撃退に大活躍するんです。イタチは突然の音に敏感なため、風鈴の音で侵入を防ぐことができます。
「えっ、風鈴でイタチが逃げるの?」と思われるかもしれませんね。
でも、この方法がとても効果的なんです。
設置方法を見てみましょう。
- 風鈴を用意する(金属製がおすすめ)
- イタチの侵入口付近に吊るす
- 風が通る場所を選ぶ
風鈴の「チリンチリン」という予測不能な音が、イタチを警戒させるんです。
特に夜行性のイタチは、静かな夜間に鳴る風鈴の音にビックリ。
「ここは危険だぞ」と感じて、近づかなくなるんです。
この方法のいいところは、見た目も涼しげなこと。
「イタチ対策しながら、夏の風情も楽しめる」なんて、一石二鳥ですよね。
注意点としては、風鈴の設置場所。
あまりにも家の中まで音が響くと、今度は人間が眠れなくなっちゃいます。
「イタチは追い払えたけど、家族が寝不足」なんて本末転倒にならないよう、適度な距離感が大切です。
また、雨風が強い日は一時的に取り外すのもいいでしょう。
「風鈴がうるさすぎて、ご近所迷惑」なんてことにならないよう気をつけましょう。
この方法は、季節を問わず使えるのも魅力。
夏は涼しげな装飾として、冬は防犯ベルの代わりとしても活躍します。
「一年中役立つイタチ対策グッズ」というわけです。
家族みんなで「どんな音色がいいかな?」「この場所はどう?」なんて相談しながら設置するのも楽しいかもしれません。
イタチ対策が、家族の思い出づくりにもなるんです。
風鈴の音色で、イタチを追い払う。
日本の伝統的な風物詩が、現代の害獣対策に一役買う。
そんな素敵なアイデア、試してみませんか?
スパイシー作戦!「唐辛子スプレー」でイタチを撃退
唐辛子を使ったスプレーで、イタチを効果的に撃退できます。イタチは辛い匂いが苦手なので、この方法がとても効果的なんです。
「えっ、唐辛子でイタチが逃げるの?」と驚く方も多いかもしれませんね。
でも、これがなかなかの威力を発揮するんです。
作り方と使い方を見てみましょう。
- 唐辛子パウダーを用意する
- 水と混ぜてスプレーボトルに入れる
- イタチの侵入経路や出没場所に吹きかける
イタチを追い払うのが目的なので、人間が触っても大丈夫な程度の辛さに。
「うわっ!辛すぎる!」なんて自分が被害者にならないよう注意しましょう。
この方法のいいところは、自然由来の材料を使うこと。
化学物質を使わないので、環境にも優しいんです。
「エコなイタチ対策だね」というわけ。
注意点としては、風向きに気をつけること。
「スプレーが自分に返ってきた!」なんてことにならないよう、風上から吹きかけましょう。
また、目に入らないよう、スプレーを使うときは保護メガネを着用するのがおすすめです。
効果は一時的なので、定期的な散布が必要です。
「雨が降ったら効果が薄れちゃうかも」という心配もあるので、天気予報をチェックしながら対策するのがコツです。
この方法は、他の動物にも効果があるのが特徴。
ネコやタヌキなど、イタチ以外の動物による被害も同時に防げるんです。
「一石二鳥どころか、一石三鳥!」なんて具合です。
ただし、唐辛子アレルギーの方は使用を控えましょう。
「イタチは追い払えたけど、今度は自分がくしゃみ止まらない」なんてことになっては本末転倒ですからね。
家族みんなで「どこに吹きかけようかな?」「この場所は要注意だよ」なんて話し合いながら対策するのも楽しいかもしれません。
イタチ対策が、家族の絆を深めるきっかけにもなるんです。
唐辛子パワーで、イタチを撃退。
スパイシーな対策で、イタチフリーの家づくりを始めましょう!