イタチ対策の動体センサーライトは?【広範囲を照らすタイプが有効】夜間の侵入を防ぎ、安全な環境を作れる

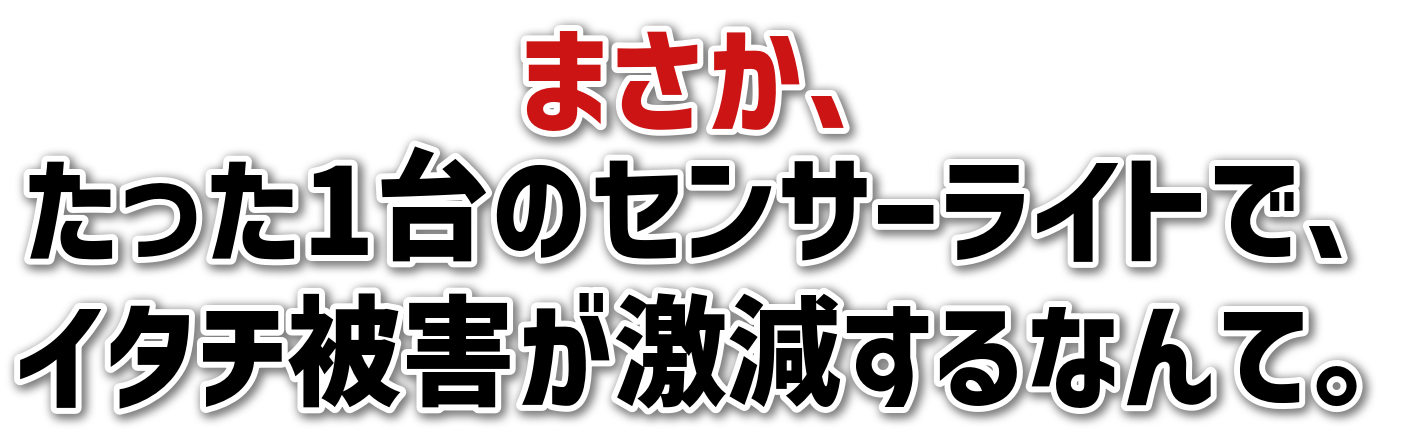
【この記事に書かれてあること】
イタチの被害に悩まされていませんか?- 広範囲を照らす動体センサーライトがイタチ対策に効果的
- 感度調整機能と防水性能が重要な選択ポイント
- イタチの侵入経路を見極めて最適な位置に設置
- 複数設置で死角をなくす完璧な防御網を構築
- 定期的なメンテナンスで長期間の安定稼働を実現
- 赤外線カメラや超音波発生器との組み合わせで効果アップ
動体センサーライトを使えば、効果的な対策が可能です。
でも、ただ設置するだけでは十分な効果が得られないかもしれません。
この記事では、イタチ対策に最適な動体センサーライトの選び方から、効果的な設置方法、さらには驚きの裏技まで詳しくご紹介します。
「もうイタチには困らない!」と胸を張れるよう、完璧な防御策を一緒に学んでいきましょう。
【もくじ】
イタチ対策の動体センサーライトの特徴と選び方

広範囲を照らすタイプが侵入防止に効果的!
広範囲を照らす動体センサーライトがイタチ対策には一番効果的です。広い範囲を明るく照らすことで、イタチの侵入を抑止できるんです。
イタチは暗がりを好む夜行性の動物。
そんなイタチにとって、パッと明るくなる光は大敵なんです。
「えっ、見つかっちゃう!」とびっくりして逃げ出してしまうわけです。
広範囲を照らすタイプの動体センサーライトには、こんな特徴があります。
- 検知角度が120度以上と広い
- 照射範囲が10メートル以上ある
- 複数のLEDライトを搭載している
例えば、庭全体や家の周りを一気に明るくできるイメージです。
ただし、注意点もあります。
広範囲を照らすタイプは消費電力が大きくなりがち。
「バッテリーの持ちが悪くなっちゃう…」という心配も出てきます。
そこで、ソーラーパネル付きのタイプを選ぶのもいいでしょう。
日中に充電して夜間使用する仕組みなら、電源の心配はありません。
広範囲を照らすタイプを選ぶときは、設置場所をよく考えましょう。
イタチの侵入経路を予想し、そこを重点的に照らせる位置に設置するのがコツです。
そうすれば、イタチ対策の効果がグンと上がりますよ。
感度調整機能付きで誤作動を防止「快適な生活」
感度調整機能付きの動体センサーライトを選ぶことで、誤作動を防ぎ快適な生活を送れます。この機能があれば、イタチの動きだけを的確に捉えられるんです。
センサーの感度が高すぎると、風で揺れる木の葉や小さな虫にも反応してしまいます。
「ピカッ、ピカッ」とやたらと点灯して、かえって困ってしまうことも。
逆に感度が低すぎると、イタチの動きを見逃してしまう可能性が。
そこで大切になるのが、感度調整機能なんです。
感度調整機能付きのセンサーライトには、こんなメリットがあります。
- イタチの動きだけを確実に検知
- 不要な点灯を減らしてバッテリー節約
- 季節や環境の変化に合わせて調整可能
使い始めは「中」に設定し、様子を見ながら調整するのがおすすめです。
例えば、庭に木が多い場合は感度を少し下げてみましょう。
「ゴソゴソ」というイタチの動きは捉えつつ、「サワサワ」という葉の揺れには反応しないよう調整できます。
また、夏と冬では周囲の環境が変わります。
そんなときも感度調整で対応できるんです。
「冬は葉っぱが落ちて見通しがよくなったから、感度を少し下げよう」なんて具合に。
感度調整機能を上手に使えば、イタチ対策と快適な生活の両立が可能になります。
それこそが、この機能の最大の魅力なんです。
バッテリー駆動か電源タイプか「設置場所で決める」
動体センサーライトを選ぶとき、バッテリー駆動か電源タイプかは設置場所で決めましょう。それぞれに長所と短所があるので、自分の環境に合わせて選ぶのがポイントです。
まず、バッテリー駆動タイプの特徴を見てみましょう。
- コンセントがない場所でも設置可能
- 配線工事が不要で手軽に取り付けられる
- 災害時でも使える
庭の奥や物置の近くなど、電源から離れた場所にも自由に設置できるんです。
一方で、電源タイプにはこんな特徴があります。
- バッテリー交換の手間がない
- 長期間の安定した動作が期待できる
- より明るい光を出せる
また、電源の心配がないので、より明るく広範囲を照らすことができます。
では、どう選べばいいのでしょうか?
ここがポイントです。
屋外の電源から離れた場所→バッテリー駆動
家の外壁など、コンセントに近い場所→電源タイプ
例えば、庭の奥にイタチが出没するなら、バッテリー駆動がおすすめ。
「ゴソゴソ…」というイタチの動きを捉えて、パッと明るく照らせます。
逆に、玄関脇にセンサーライトを付けたいなら、電源タイプが便利。
「ピカッ」と明るく照らして、イタチも人間も安心です。
設置場所をよく考えて選べば、イタチ対策がぐっと効果的になりますよ。
防水性能は必須!「屋外設置でも安心」
屋外に設置する動体センサーライトには、防水性能が必須です。雨や雪に負けない防水設計なら、屋外でも安心して使えるんです。
イタチは屋外から侵入してくるもの。
だから、センサーライトも屋外に設置することが多いんです。
でも、屋外となると天候の影響を受けやすい。
「雨が降ったらセンサーが壊れちゃうかも…」なんて心配になりますよね。
そこで重要になるのが防水性能なんです。
防水性能の高い動体センサーライトには、こんな特徴があります。
- IP65以上の防水・防塵規格を持つ
- シリコンなどでしっかり密閉されている
- 電池ボックスも防水処理されている
この規格以上なら、雨はもちろん、庭の水まきにも耐えられるんです。
例えば、大雨の日。
普通のライトなら「ジャー」という雨音とともに壊れてしまうかもしれません。
でも、防水性能の高いセンサーライトなら、雨にも負けず「ピカッ」とイタチの動きを捉えてくれるんです。
冬の雪対策にも有効です。
雪が積もっても、融けた水が内部に入り込むことはありません。
「シンシン」と雪が降る中でも、しっかりイタチを警戒してくれますよ。
ただし、注意点もあります。
防水性能が高いほど、価格も高くなる傾向があります。
でも、長期的に見れば故障のリスクが減るので、結果的にはお得になる場合が多いんです。
屋外設置を考えているなら、防水性能はしっかりチェックしましょう。
それが、長く安心してイタチ対策を続けるコツになるんです。
ソーラーパネル付きは「長期運用にオススメ」
ソーラーパネル付きの動体センサーライトは、長期運用に最適です。太陽の力を利用するので、電池交換の手間がなく、環境にも優しいんです。
イタチ対策は長期戦。
毎日の電池交換や充電は、正直面倒ですよね。
「あ、電池切れだ!」と気づいたときには、もうイタチが侵入していたなんてことも。
そんな悩みを解決してくれるのが、ソーラーパネル付きのセンサーライトなんです。
ソーラーパネル付きのメリットは、こんなところです。
- 電池交換や充電の手間が不要
- 電気代がかからず経済的
- 設置場所を選ばない
- 停電時でも使える
「チャージ」と「使用」のサイクルが自動的に繰り返されるので、とても便利なんです。
例えば、庭の奥にイタチの通り道があるとしましょう。
電源のない場所でも、ソーラーパネル付きなら設置OK。
日中はコッソリ充電し、夜になれば「ピカッ」とイタチの動きを捉えてくれるんです。
ただし、注意点もあります。
日当たりの悪い場所や、長期間の曇天が続く地域では、充電不足になる可能性があります。
そんなときは、バックアップ用の充電池を用意しておくといいでしょう。
また、冬場は日照時間が短くなるので、充電効率が落ちることも。
でも、最近の製品は性能が向上しているので、多くの場合は問題なく使えます。
ソーラーパネル付きのセンサーライトを選べば、「エコで経済的」なイタチ対策が可能になります。
長期戦のイタチ対策には、ピッタリの選択肢と言えるでしょう。
動体センサーライトの効果的な設置方法とメンテナンス

イタチの侵入経路を見極めて「最適な位置に設置」
イタチの侵入経路を事前に把握し、そこに動体センサーライトを設置するのが最も効果的です。まずは、イタチがどこから侵入しているのか観察してみましょう。
「ゴソゴソ」と音がする場所や、足跡が残っている場所をチェックします。
よく見られる侵入経路には次のようなものがあります。
- 屋根や軒下の隙間
- 換気口や排水口
- 樹木や電線から伝って侵入
- 地面の穴や石垣の隙間
例えば、屋根の隙間からの侵入が多い場合は、その近くの壁に取り付けるのがおすすめです。
「ピカッ」と光れば、イタチはびっくりして逃げ出すでしょう。
設置する高さも重要です。
イタチの目線よりも少し高い位置、地上から2〜3メートルくらいが適しています。
こうすることで、イタチの動きを確実に捉えられるんです。
また、センサーの向きにも注意が必要です。
イタチの侵入経路に向けて、少し下向きに設置するのがコツです。
「こっちから来るぞ!」とイタチの動きを逃さず捉えられます。
ただし、設置場所によっては思わぬ誤作動も。
例えば、道路に面した場所だと、車のヘッドライトで点灯してしまうかもしれません。
そんなときは、センサーの向きを少し変えたり、感度を調整したりして対応しましょう。
イタチの侵入経路をしっかり見極めて最適な位置に設置すれば、動体センサーライトの効果は抜群です。
イタチも「ここはもう危険だ!」と学習して、寄り付かなくなるはずですよ。
複数設置でイタチの死角をなくす「完璧な防御網」
動体センサーライトを複数設置することで、イタチの侵入を防ぐ完璧な防御網を作り上げることができます。1台だけだと、どうしても死角ができてしまいます。
「ここなら大丈夫」とイタチに隙を与えてしまうかもしれません。
でも、複数台を戦略的に配置すれば、そんな心配はありません。
複数設置の効果的な方法を見てみましょう。
- 家の四隅に1台ずつ設置
- 侵入経路として考えられる場所を重点的にカバー
- センサーの検知範囲が少し重なるように配置
- 高さの異なる位置に設置して立体的に防御
下からのアプローチも、木から飛び移ってくるパターンも、しっかりカバーできます。
また、庭が広い場合は、家の周りだけでなく、庭の入り口付近にも設置するといいでしょう。
「ピカッ、ピカッ」と次々に光るライトに、イタチもたじたじです。
複数設置の際に気をつけたいのが、各ライトの感度設定です。
近すぎる位置に設置すると、1つが反応したときに他のライトも一斉に点灯してしまい、電池の消耗が早くなってしまいます。
適度な間隔を保ち、感度も調整しながら設置しましょう。
「でも、たくさん買うのはお金がかかるなぁ」と心配する方もいるかもしれません。
確かに初期費用は高くなりますが、長期的に見ればイタチ被害を防ぐことができ、結果的にはコスト削減につながります。
複数の動体センサーライトで完璧な防御網を築けば、イタチも「この家は危険すぎる!」と諦めてどこかへ行ってしまうでしょう。
あなたの家を守る強力な味方になってくれるはずです。
高さ調整で検知範囲を最適化「イタチを逃さない」
動体センサーライトの高さを適切に調整することで、イタチの動きを確実に捉え、逃がさない防御体制を作ることができます。高さ調整のポイントは、イタチの行動範囲をしっかりカバーすることです。
イタチは地面を這うように動くこともあれば、木や塀を伝って高い所を移動することもあります。
そんなイタチの多様な動きに対応するには、高さの調整が欠かせません。
効果的な高さ調整の方法を見てみましょう。
- 地上2〜3メートルの高さに設置
- センサー部分を少し下向きに傾ける
- 侵入経路の高さに合わせて調整
- 複数のライトを異なる高さに設置
「よいしょ」と塀を乗り越えた瞬間に「ピカッ」と光れば、イタチもびっくり仰天です。
また、地面からの侵入が心配な場合は、少し低めの位置に設置するのがおすすめ。
センサーを下向きにして、地面すれすれの動きも見逃さないようにしましょう。
高さ調整で気をつけたいのが、誤作動の問題です。
低すぎると小動物や落ち葉にも反応してしまいますし、高すぎるとイタチの動きを見逃してしまう可能性があります。
設置後は様子を見て、必要に応じて微調整することが大切です。
「でも、一度設置したら高さ変更は難しいのでは?」と思う方もいるでしょう。
そんなときは、取り付け金具を工夫してみましょう。
上下に可動するブラケットを使えば、後から高さ調整がしやすくなりますよ。
高さをうまく調整すれば、イタチの動きを逃さず捉えられます。
「どこを通っても見つかっちゃう!」とイタチも困ってしまうはず。
あなたの家を守る頼もしい見張り番になってくれることでしょう。
定期的な清掃と点検で「長期間の安定稼働」を実現
動体センサーライトを長期間安定して稼働させるには、定期的な清掃と点検が欠かせません。これらのメンテナンスを怠ると、せっかく設置したのに性能が落ちてしまい、イタチ対策の効果が薄れてしまうんです。
まずは、清掃の重要性について考えてみましょう。
屋外に設置された動体センサーライトは、ホコリや虫の死骸、鳥のフンなどで汚れやすいんです。
センサー部分が汚れると、検知性能が落ちてしまい、イタチが近づいても反応しなくなってしまうかもしれません。
効果的な清掃方法はこんな感じです。
- 柔らかい布で全体をやさしく拭く
- センサー部分は特に丁寧に清掃
- 水で薄めた中性洗剤を使用(必要な場合のみ)
- 清掃後は、しっかり乾かす
「めんどくさいなぁ」と思うかもしれませんが、定期的に行えば1回あたりの作業は数分で済みますよ。
次に、点検の重要性です。
動体センサーライトは精密機器なので、時間が経つと少しずつ性能が変化することがあります。
定期的な点検で、以下のような項目をチェックしましょう。
- センサーの反応具合
- ライトの明るさ
- バッテリーの残量(電池式の場合)
- 取り付け部分のゆるみ
- 防水パッキンの劣化
「ちょっと動作がおかしいな」と感じたら、すぐに確認することが大切です。
冬場は特に注意が必要です。
寒さや雪の影響で、思わぬトラブルが起きることも。
「カチカチ」と凍ってしまったり、雪に埋もれたりしていないか、こまめにチェックしましょう。
定期的な清掃と点検を行えば、動体センサーライトは長期間安定して稼働し続けます。
「ピカッ」という光で、イタチをしっかり撃退してくれるはずですよ。
バッテリー交換のタイミング「性能低下に注意」
動体センサーライトのバッテリー交換は、性能維持のために重要なポイントです。適切なタイミングでバッテリーを交換することで、イタチ対策の効果を長期間持続させることができます。
バッテリー式の動体センサーライトは便利ですが、使い続けるとだんだん電池が弱ってきます。
「最近、ライトの明るさが落ちたな」「センサーの反応が遅くなった気がする」といった症状が現れたら、バッテリー交換のサインかもしれません。
バッテリー交換のタイミングを見極めるポイントはこんな感じです。
- ライトの明るさが明らかに暗くなった
- 点灯時間が短くなった
- センサーの反応が鈍くなった
- 使用開始から6ヶ月〜1年程度経過した
例えば、人や動物の往来が多い場所に設置すると、頻繁に点灯するのでバッテリーの消耗も早くなります。
「うちは田舎だから大丈夫かな」と思っても、意外と早く消耗することもあるので注意が必要です。
バッテリー交換の際は、以下の点に気をつけましょう。
- メーカー推奨の電池を使用する
- 全ての電池を同時に交換する
- 電池の向きを間違えないよう注意する
- 交換後は必ず動作確認を行う
そんな方には、充電式電池の使用をおすすめします。
初期費用は少し高くなりますが、長期的にはコスト削減になりますよ。
また、ソーラーパネル付きの機種を選べば、バッテリー交換の手間がさらに省けます。
「太陽の力で勝手に充電してくれる」なんて、とっても便利ですよね。
バッテリーの状態に気を配り、適切なタイミングで交換することで、動体センサーライトは常に最高の性能を発揮します。
イタチも「この家はいつも用心深いな」と感じて、近づかなくなるでしょう。
定期的なチェックを忘れずに、しっかりとイタチ対策を続けていきましょう。
動体センサーライトを活用したイタチ対策の裏技と応用

赤外線カメラと連動させて「行動パターンを把握」
動体センサーライトと赤外線カメラを連動させることで、イタチの行動パターンを詳細に把握し、より効果的な対策が可能になります。まず、赤外線カメラをイタチが出没しそうな場所に設置します。
例えば、庭の隅や家の周りの通路など、イタチがよく通りそうな場所がおすすめです。
「ここからイタチが来るんじゃないかな?」と予想する場所ですね。
赤外線カメラは夜間でもクリアな映像を撮影できるので、夜行性のイタチの動きをしっかり捉えられます。
数日間観察することで、イタチがどの時間帯に、どのルートで侵入してくるのかが分かってきます。
- イタチの侵入時間帯を特定
- よく使う移動ルートを把握
- 餌を探す場所や休憩場所を発見
「ここを通るんだな」という場所に的確にライトを設置すれば、イタチを効果的に撃退できます。
さらに、赤外線カメラと動体センサーライトを連動させる方法もあります。
カメラが動きを検知したら自動的にライトが点灯する仕組みです。
「ピカッ」とライトが光れば、イタチもびっくり。
「ここは危険だ!」と学習させることができます。
ただし、注意点もあります。
赤外線カメラの設置には、プライバシーに配慮する必要があります。
近隣の家や道路を映さないよう、カメラの向きには気をつけましょう。
この方法を使えば、イタチの習性を利用した、より賢い対策が可能になります。
「イタチの気持ちになって考える」ことで、効果的な防御策が見えてくるんです。
赤外線カメラと動体センサーライトの連携で、イタチ対策をワンランクアップさせましょう。
ライトの色を変えて「イタチが苦手な青や紫に」
イタチが苦手な色、特に青や紫の光を使うことで、より効果的な撃退が可能になります。動体センサーライトの色を工夫するだけで、イタチ対策の効果がグンと上がるんです。
イタチは人間とは違う色の感じ方をします。
特に青や紫の光に対して敏感で、これらの色を見ると不快に感じるんです。
「うわ、この光はイヤだ!」とイタチが思うわけです。
では、どんな色のライトを選べばいいのでしょうか?
- 青色LED:波長が短く、イタチに強い不快感を与える
- 紫色LED:青色よりさらに波長が短く、より効果的
- 白色LED:青色成分を含むため、ある程度の効果あり
これなら、昼は普通の白色光で使い、夜はイタチ対策モードで青や紫の光に切り替えるといった使い方ができます。
ただし、注意点もあります。
あまりに強い青や紫の光は、人間の目にも良くありません。
設置する場所や光の強さには気をつけましょう。
「イタチは追い払いたいけど、自分たちも快適に過ごしたい」というバランスが大切です。
また、青や紫の光を使う際は、近隣への配慮も忘れずに。
「うちの庭が毎晩ディスコみたいに光ってる!」なんて苦情が来ないよう、光の向きや強さを調整しましょう。
効果を高めるコツは、動体センサーの感度設定にもあります。
イタチサイズの動物を確実に検知し、かつ小さな虫などには反応しないよう、中程度の感度に設定するのがおすすめです。
青や紫の光を上手に活用すれば、イタチにとって「ここは居心地が悪い場所だ」と感じさせることができます。
光の色という、意外と見落としがちなポイントにこだわることで、イタチ対策の効果をさらに高められるんです。
超音波発生器と組み合わせて「光と音でダブル撃退」
動体センサーライトと超音波発生器を組み合わせることで、光と音の二重の防御でイタチを効果的に撃退できます。この方法を使えば、イタチに「ここは危険な場所だ」としっかり認識させることができるんです。
まず、超音波発生器について説明しましょう。
これは人間には聞こえない高い周波数の音を出す装置です。
イタチはこの音を非常に不快に感じ、その場所から離れようとします。
「キーン」という音が頭の中で鳴り響いているような感覚でしょうか。
動体センサーライトと超音波発生器を連動させる方法は以下の通りです:
- センサーが動きを検知すると、ライトが点灯
- 同時に超音波発生器がオンになる
- 光と音の二重の刺激でイタチを驚かせる
- 一定時間後、両方の装置が自動的にオフに
目には突然の光、耳には不快な音。
「うわっ、なんだこれは!」とイタチも動揺してしまうでしょう。
設置する際のポイントは、両方の装置の有効範囲を重ねることです。
例えば、庭の入り口付近に動体センサーライトを設置し、その近くに超音波発生器を配置します。
こうすることで、イタチが侵入しようとした瞬間に「ピカッ」と光り、同時に「キーン」という超音波が発生するわけです。
ただし、使用する際は近隣への配慮も必要です。
超音波は人間には聞こえませんが、ペットには影響がある可能性があります。
特に、お隣で犬や猫を飼っている場合は要注意。
事前に説明し、了解を得ておくのがマナーです。
また、超音波発生器の使用は適度に行いましょう。
常時オンにしていると、イタチが慣れてしまう可能性があります。
動体センサーと連動させ、必要なときだけ作動させるのがコツです。
この「光と音のダブル撃退法」を使えば、イタチに強烈な印象を与えることができます。
「あの場所は危険だ」という記憶を植え付けることで、長期的な撃退効果が期待できるんです。
イタチ対策の切り札として、ぜひ試してみてください。
スマートフォンと連動「リアルタイムで侵入を把握」
動体センサーライトをスマートフォンと連動させることで、イタチの侵入をリアルタイムで把握し、即座に対応することができます。この方法を使えば、家にいなくてもイタチの動きを監視できるんです。
最近のスマート家電の技術を活用すれば、動体センサーライトとスマートフォンを簡単に連携させることができます。
その仕組みはこんな感じです:
- センサーが動きを検知すると、ライトが点灯
- 同時に、スマートフォンに通知が送られる
- アプリで映像を確認したり、遠隔で操作したりできる
アプリを開いてみると、庭にイタチが侵入している様子が映っています。
「おや、また来たな」と思いつつ、アプリから追加のライトを点灯させたり、録音した威嚇音を流したりすることができるんです。
この方法の大きなメリットは、リアルタイムで状況を把握し、対応できること。
「留守中に何が起きているんだろう…」という不安も解消されます。
また、イタチの侵入パターンを長期的に観察することで、より効果的な対策を立てられるようになります。
設定方法は意外と簡単です:
- スマート対応の動体センサーライトを購入
- 専用アプリをスマートフォンにインストール
- WiFiを使ってライトとスマートフォンを接続
- 通知設定やカメラの角度などを調整
常時接続するため、ライトの電池の消耗が早くなる可能性があります。
ソーラーパネル付きの機種を選んだり、こまめに充電したりする必要があるでしょう。
また、セキュリティにも気をつけましょう。
悪意のある人に映像を見られないよう、強力なパスワードを設定するなど、適切な対策が必要です。
スマートフォンとの連動で、イタチ対策はより賢く、より効率的になります。
「今どんな状況なんだろう」とやきもきすることもなくなりますよ。
テクノロジーの力で、イタチとの知恵比べに勝利しましょう。
ダミーのセンサーライトで「費用対効果アップ」
ダミーの動体センサーライトを活用することで、イタチ対策の費用対効果を大幅にアップさせることができます。本物のセンサーライトと組み合わせて使うことで、より広範囲をカバーしつつ、コストを抑えられるんです。
ダミーセンサーライトとは、本物そっくりの外見をしているけれど、実際には動作しないライトのこと。
でも、イタチにはそれが本物か偽物かは分かりません。
「あそこにもライトがある!危険だ!」と思わせることができるんです。
ダミーライトの効果的な使い方はこんな感じです:
- 本物のセンサーライトと交互に配置
- 死角になりやすい場所にダミーを設置
- 定期的に位置を変えて、慣れを防ぐ
イタチからすれば、「どこを通っても光るかもしれない」と警戒するわけです。
ダミーライトのメリットは、何と言ってもコストパフォーマンスの高さ。
本物の動体センサーライトは電池交換や故障の可能性がありますが、ダミーはメンテナンスフリー。
「あれ、また電池切れか…」なんてストレスとは無縁です。
ただし、ダミーライトだけに頼るのは危険です。
イタチは賢い動物なので、すぐに「あ、これは偽物だ」と気づいてしまうかもしれません。
本物とダミーを上手に組み合わせることが大切です。
効果を高めるコツはいくつかあります:
- 本物そっくりのデザインを選ぶ
- 時々、ダミーの近くで懐中電灯を光らせる
- ダミーにも反射板やレンズを付ける
- 定期的に位置を変えて、新鮮さを保つ
イタチ対策の目的は、彼らを傷つけることではなく、単に近づかせないこと。
ダミーライトはその目的を達成するための、賢い戦略の一つなんです。
ダミーセンサーライトを活用すれば、少ない予算でも広範囲のイタチ対策が可能になります。
本物とダミーを巧みに組み合わせて、イタチを寄せ付けない環境を作り上げましょう。
これぞまさに「知恵は力なり」というわけです。