イタチを安全に捕まえるコツは?【餌付け式トラップが効果的】正しい方法で、ストレスを与えず捕獲できる

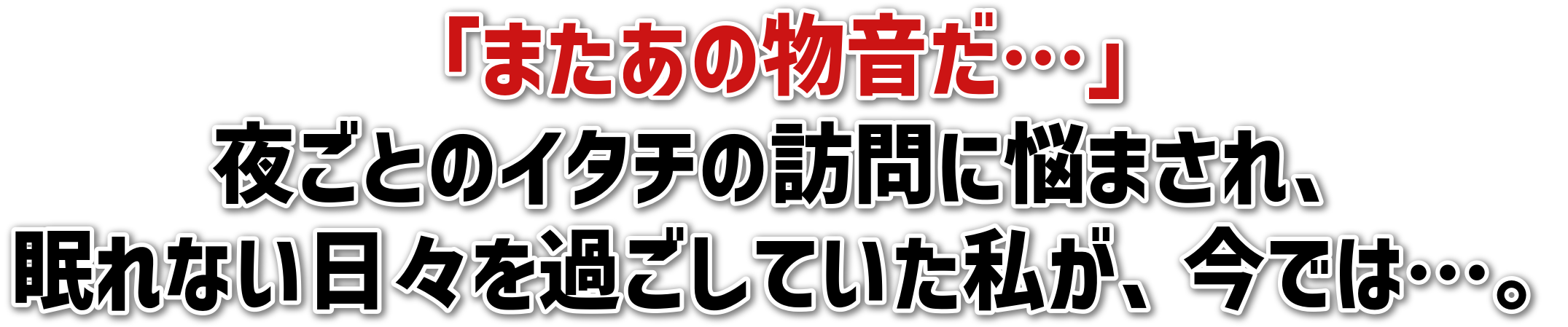
【この記事に書かれてあること】
イタチの被害に悩まされていませんか?- 箱型トラップがイタチ捕獲に最適
- 餌付け式トラップで捕獲成功率が約70%にアップ
- 捕獲時は厚手の手袋着用など安全対策が重要
- 捕獲したイタチは2キロ以上離れた場所で放獣
- 再侵入防止には隙間封鎖と臭い対策が効果的
家の中に侵入されて困っている方も多いはず。
でも、大丈夫です。
イタチを安全に捕まえる方法があるんです。
この記事では、効果的で安心な捕獲方法をご紹介します。
餌付け式トラップの使い方や、捕獲時の注意点、さらには再侵入を防ぐ方法まで。
これを読めば、あなたもイタチ対策のプロになれるかも!
さあ、一緒にイタチ問題を解決しましょう。
【もくじ】
イタチを安全に捕まえるコツとは?被害解決への第一歩
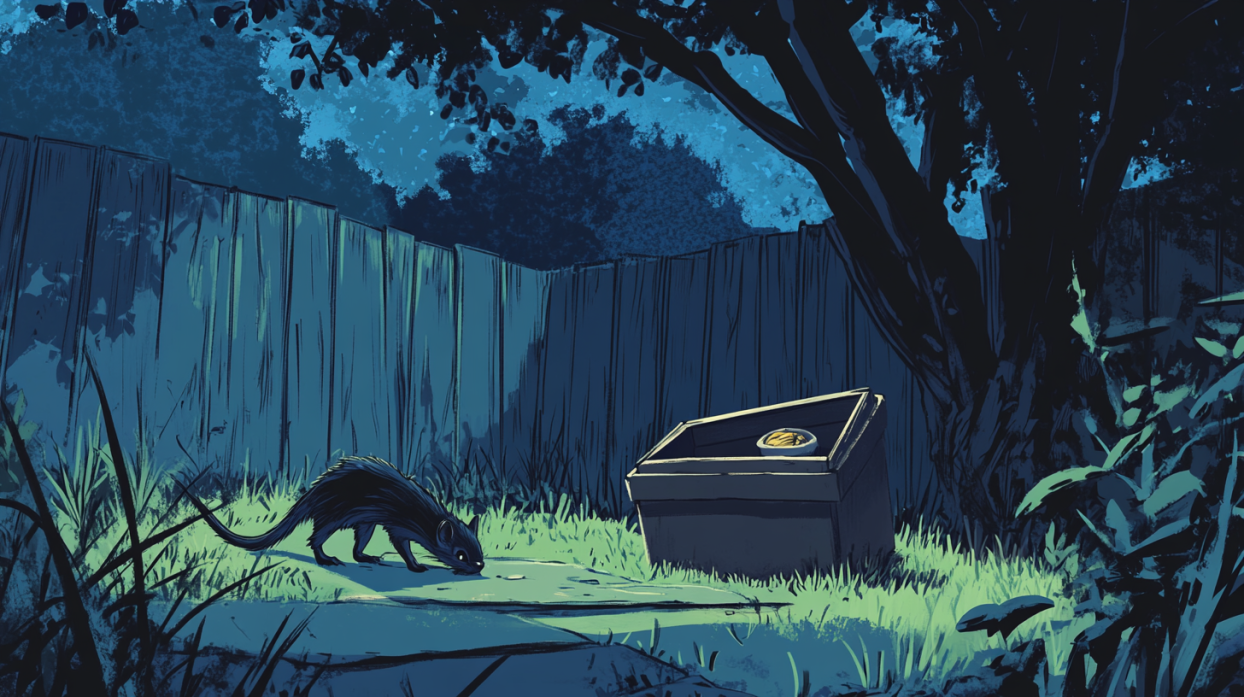
イタチ捕獲に最適!「箱型トラップ」の特徴と選び方
イタチ捕獲には箱型トラップが最適です。安全性が高く、イタチにもやさしい捕獲方法なんです。
箱型トラップは、両端が開いた長方形の箱で、イタチが中に入ると扉が閉まる仕組みになっています。
「えっ、そんな簡単な仕掛けで捕まるの?」と思うかもしれませんが、意外と効果的なんです。
では、どんな箱型トラップを選べばいいのでしょうか?
サイズ選びがとっても大切です。
イタチがゆったり入れる大きさがポイントです。
具体的には、以下の寸法が目安になります。
- 長さ:60?80センチ
- 幅:15?20センチ
- 高さ:15?20センチ
「金属製のものがいいかな?」と考える人も多いですが、プラスチック製でも十分です。
むしろ、軽くて扱いやすいプラスチック製がおすすめです。
トラップの扉の仕組みも重要です。
イタチが入ると自動で閉まる構造が理想的です。
手動のものだと、タイミングを逃してしまう可能性があるからです。
「でも、イタチを傷つけちゃわないかな?」と心配する人もいるでしょう。
大丈夫です。
箱型トラップは、イタチにストレスを与えにくい設計になっているんです。
閉じ込められても、ガチャガチャと暴れることが少ないんです。
選ぶときは、通気性も確認しましょう。
イタチが呼吸しやすいように、小さな穴が開いているものを選んでくださいね。
餌付け式トラップで成功率アップ!確実な捕獲方法
餌付け式トラップを使えば、イタチの捕獲成功率がぐんとアップします。なんと、約70%の確率で捕獲できるんです!
餌付け式トラップの魅力は、イタチを自然に誘い込める点です。
「イタチさん、どうぞこちらへ」と招待しているような感じですね。
急に捕まえようとするより、ずっと効果的なんです。
では、具体的な方法を見ていきましょう。
- トラップを設置する場所を決める(イタチの通り道や痕跡が見つかる場所)
- トラップの中に餌を置く(生魚や鶏肉がおすすめ)
- トラップの扉を開けたままにする
- 2?3日間、餌だけを取り替える(この間、扉は閉めない)
- イタチが餌に慣れてきたら、トラップを作動させる
でも、これが重要なポイントなんです。
イタチに「ここは安全な場所」と思わせることで、警戒心を解くんです。
餌の選び方も大切です。
イタチは肉食動物なので、生魚や鶏肉が大好物。
特に、魚の缶詰を開けたまま置くと、強い匂いでイタチを誘い込めます。
これ、実はすごく効果的な裏技なんです!
ただし、注意点もあります。
餌を長時間放置すると腐敗の危険があるので、毎日新しいものに取り替えましょう。
「ちょっと面倒くさいなぁ」と感じるかもしれませんが、捕獲成功のためには大切な作業です。
また、周辺の衛生管理も忘れずに。
餌の匂いで他の動物が寄ってくる可能性もあるので、トラップ周辺はきれいに保っておきましょう。
安全第一!イタチ捕獲時の注意点と防護対策
イタチ捕獲時は安全が何より大切です。適切な防護対策を取れば、安心して捕獲作業ができます。
まず、必ず厚手の手袋を着用しましょう。
イタチは驚くと噛みついたり引っかいたりすることがあります。
「え?そんなに危険なの?」と思うかもしれませんが、用心に越したことはありません。
次に、長袖・長ズボンの服装を心がけましょう。
肌の露出を最小限に抑えることで、万が一の接触時も安全です。
捕獲器を扱う際の注意点も押さえておきましょう。
- 捕獲器を急に動かさない
- 大きな音を立てない
- 急な動きを避ける
イタチが落ち着いていれば、作業もスムーズに進みます。
もし、イタチが捕獲器の中で暴れだしたらどうすればいいでしょうか?
そんなときは、暗い布で捕獲器を覆うのが効果的です。
暗くなると、イタチは落ち着きを取り戻します。
「でも、もし噛まれたらどうしよう…」と心配な人もいるでしょう。
万が一噛まれてしまった場合は、すぐに傷口を石鹸で洗い、消毒しましょう。
そして、念のため医療機関を受診することをおすすめします。
捕獲作業は、できれば2人以上で行うのがベストです。
1人が捕獲器を扱い、もう1人が周囲の安全を確認する、という具合です。
「え?そこまで必要?」と思うかもしれませんが、これで作業の安全性がぐっと高まるんです。
最後に、作業後の手洗いとうがいも忘れずに。
衛生面でも気を付けることで、より安全な捕獲作業が実現できます。
絶対NG!イタチ捕獲で「やってはいけない」危険行為
イタチ捕獲には、絶対に避けるべき危険な行為があります。これらを知っておくことで、安全で効果的な捕獲ができるんです。
まず、絶対にやってはいけないのが素手での捕獲です。
「ちょっとぐらいなら大丈夫かな」なんて思っちゃダメ!
イタチは驚くと噛みついたり引っかいたりします。
ケガの危険があるだけでなく、病気感染のリスクも高まってしまうんです。
次に、違法な毒餌の使用も絶対NGです。
「早く退治したいから…」という気持ちはわかりますが、これは逆効果。
なぜなら:
- イタチ以外の動物も被害を受ける
- 生態系のバランスを崩す
- 法律違反で罰せられる可能性がある
例えば、棒でつついたり、大声で脅したりするのはNG。
イタチを追い詰めると、逆に攻撃的になる可能性があるんです。
「イタチを捕まえたら遠くに放すのがいいんじゃない?」と考える人もいるでしょう。
でも、知らない土地に放すのは実はイタチにとって残酷なんです。
慣れない環境でイタチが生き延びるのは難しいからです。
それから、捕獲したイタチを長時間放置するのも問題です。
「ちょっと様子見しよう」なんて思っちゃダメ。
イタチにとって大きなストレスになります。
捕獲したら、できるだけ早く適切な場所に放獣しましょう。
最後に、子イタチを見つけても、むやみに触らないでください。
近くに親イタチがいる可能性が高いんです。
親イタチは子どもを守ろうとして攻撃的になることがあります。
これらの「やってはいけない」ことを避けることで、イタチにも人間にも優しい捕獲ができるんです。
安全第一で、適切な方法でイタチ対策を進めていきましょう。
イタチにストレスを与えない!効果的な捕獲と対応法

捕獲器内のイタチを落ち着かせる「3つの秘策」
イタチを落ち着かせるには、暗さ、静けさ、そして安心感が大切です。これらを上手に活用することで、イタチのストレスを軽減できるんです。
まず、暗い環境を作ることが重要です。
捕獲器全体を暗い布で覆ってみましょう。
「え?布をかけるだけ?」と思うかもしれませんが、これがとても効果的なんです。
イタチは暗い場所を好むので、布をかけることで安心感を与えられます。
次に、静かな場所に置くことです。
人や車の往来が少ない場所を選びましょう。
ガヤガヤとした場所だと、イタチはびくびくしてしまうんです。
静かな場所なら、イタチもホッと一息つけるはず。
最後に、水と餌を少量提供することです。
「捕まえたのに餌をあげるの?」と驚くかもしれません。
でも、これが安心感を与える秘訣なんです。
小さな容器に水を入れ、イタチの好物である生魚や鶏肉を少量置いてあげましょう。
ここで注意したいのは、長時間放置しないことです。
定期的に様子を見て、必要に応じて水や餌を補充しましょう。
でも、あまり頻繁に近づくとイタチが警戒してしまうので、バランスが大切です。
この3つの秘策を実践すれば、イタチもきっと「ほっ」と落ち着けるはずです。
優しい気持ちで接することで、イタチにも人間にも優しい捕獲が実現できるんです。
捕獲後の移動時「ストレス軽減テクニック」とは?
イタチを移動させる際のストレス軽減には、静かな取り扱いと外部刺激の最小化がポイントです。これらを意識することで、イタチにも優しい移動が可能になるんです。
まず大切なのは、捕獲器を揺らさずに静かに運ぶことです。
「急いでいるから早く移動しなきゃ」と思っても、ゆっくり丁寧に運びましょう。
急な動きや揺れは、イタチにとって大きなストレスになるんです。
まるで赤ちゃんを抱っこするような感覚で、そっと運んでいきます。
次に、移動中は捕獲器を布で覆うことをおすすめします。
これは外部刺激を遮断する効果があります。
「え?さっきも布をかけたよね?」と思うかもしれません。
でも、移動中はより重要なんです。
周りの景色が急に変わったり、明るさが変化したりすると、イタチはびっくりしてしまいます。
布をかけることで、そんなストレスを軽減できるんです。
また、静かな環境を維持することも忘れずに。
移動中は大きな音を立てないよう注意しましょう。
車で運ぶ場合は、ラジオの音量を下げたり、急ブレーキを避けたりするのもポイントです。
さらに、温度管理にも気を配りましょう。
真夏や真冬は特に注意が必要です。
車内が極端に暑くなったり寒くなったりしないよう、適切な温度を保つことが大切です。
これらのテクニックを使えば、イタチのストレスを大幅に軽減できます。
「イタチさん、ゆっくり休んでいってね」という気持ちで、優しく移動させてあげましょう。
そうすれば、イタチも穏やかな気持ちで過ごせるはずです。
イタチvsハクビシン!捕獲難易度の違いに注目
イタチとハクビシンの捕獲難易度には、大きな違いがあります。イタチの方が捕獲しやすいのが特徴なんです。
まず、体の大きさに注目してみましょう。
イタチは体長30?40センチ程度と小柄です。
一方、ハクビシンは体長50?60センチとかなり大きいんです。
「サイズが違うだけで何が変わるの?」と思うかもしれません。
実は、これが捕獲難易度に大きく影響するんです。
イタチは小さいため、比較的小型の捕獲器で対応できます。
でも、ハクビシンは大きな捕獲器が必要で、設置や移動が大変なんです。
まるで、小さな箱と大きな箱を運ぶ違いみたいなものですね。
次に、行動パターンの違いも重要です。
イタチは好奇心旺盛で、新しいものにも興味を示します。
そのため、捕獲器に入りやすい傾向があります。
一方、ハクビシンは用心深く、新しいものを警戒する性質があります。
- イタチ:好奇心旺盛、捕獲器に入りやすい
- ハクビシン:用心深い、新しいものを警戒する
イタチは主に小動物や魚を好みます。
これらは捕獲器の餌として使いやすいんです。
一方、ハクビシンは果物や野菜も好むため、餌の選択肢が広すぎて効果的な誘引が難しいことがあります。
捕獲成功率で比べると、適切な方法を使えばイタチは約70%、ハクビシンは約50%程度と言われています。
「えっ、そんなに違うの?」と驚くかもしれませんね。
このように、イタチとハクビシンでは捕獲の難しさが異なります。
イタチの方が比較的捕まえやすいので、初心者の方にはイタチ対策から始めるのがおすすめです。
ハクビシン対策は、イタチでの経験を積んでから挑戦するのが良いでしょう。
昼vs夜!イタチの捕獲に適した時間帯を比較
イタチ捕獲には、夜間が圧倒的に有利です。なんと、夜間の捕獲成功率は約80%にも上るんです。
対して昼間は約20%程度。
この差、驚きませんか?
なぜこんなに違うのか、その秘密はイタチの生態にあります。
イタチは夜行性の動物なんです。
つまり、夜になると活発に動き回るわけです。
「ああ、だから夜の方が捕まえやすいのか!」とピンときた方も多いでしょう。
夜間のイタチの行動を想像してみてください。
辺りが暗くなると、こっそりと巣穴から顔を出します。
そして、ぴょこぴょこと餌を探して歩き回るんです。
この時間帯こそ、イタチが捕獲器に近づく絶好のチャンス!
一方、昼間のイタチはどうでしょうか。
ほとんどの時間を巣穴で過ごし、ぐっすり眠っていることが多いんです。
「寝ている動物を捕まえるのは難しそう…」そう思いますよね。
その通りなんです。
では、具体的にどんな時間帯が狙い目なのでしょうか。
- 日没直後:イタチが活動を始める時間帯
- 深夜:イタチの活動が最も活発な時間
- 夜明け前:餌を求めて最後の活動をする時間
この時間帯に餌付き捕獲器を仕掛けると、グッと効果が上がります。
ただし、注意点もあります。
夜間の作業は危険が伴うこともあるので、安全には十分気をつけましょう。
懐中電灯を用意したり、できれば2人以上で行動したりするのがおすすめです。
「え?じゃあ昼間は全く意味ないの?」そんなことはありません。
昼間は捕獲器の設置や餌の交換など、準備作業に最適な時間帯です。
夜に向けての段取りを整える大切な時間として活用しましょう。
このように、夜と昼にはそれぞれの役割があります。
イタチの習性を理解し、時間帯に合わせた対策を行うことで、効果的な捕獲が可能になるんです。
生餌vs加工餌!イタチを誘う最強のエサ対決
イタチ捕獲の成功率を左右する重要な要素、それが餌選びです。生餌と加工餌、どちらがイタチを誘うのに効果的なのでしょうか。
結論から言うと、生餌の方が圧倒的に効果的なんです。
生餌の捕獲成功率は約60%。
対して加工餌は約40%程度です。
「え、そんなに違うの?」と驚く方も多いでしょう。
この差は、イタチの本能に深く関係しているんです。
イタチは野生動物。
自然界では生きた獲物を捕まえて食べる習性があります。
つまり、新鮮な生餌の匂いに強く惹かれるんです。
特に効果的なのは以下のような生餌です。
- 小魚(イワシやアジなど)
- 鶏肉の切れ端
- 鶏の内臓
- ウズラの卵
まるで「美味しそうな匂いがする!」とイタチが鼻を鳴らしているように想像できますね。
一方、加工餌はどうでしょうか。
缶詰やドライフードなど、人間が加工した餌です。
確かにイタチも食べはしますが、生餌ほどの誘引力はありません。
イタチにとっては「まあ、食べられなくもない」程度の魅力しかないんです。
ただし、生餌にも注意点があります。
腐りやすいので、こまめな交換が必要です。
「え、面倒くさそう…」と思う方もいるでしょう。
でも、捕獲成功率を上げるためには、この手間を惜しまないことが大切なんです。
また、生餌の取り扱いには衛生面で注意が必要です。
手袋を着用し、使用後はしっかり手を洗いましょう。
一方、加工餌のメリットは取り扱いの簡単さです。
腐りにくいので、頻繁な交換が不要です。
時間や手間をかけられない場合は、加工餌も選択肢の一つになりますね。
結局のところ、状況に応じて餌を選ぶのが賢明です。
時間と手間をかけられるなら生餌、簡単に済ませたいなら加工餌。
どちらを選んでも、イタチの好みを考えて餌を選ぶことが捕獲成功への近道なんです。
捕獲成功後の適切な対処と再侵入防止策
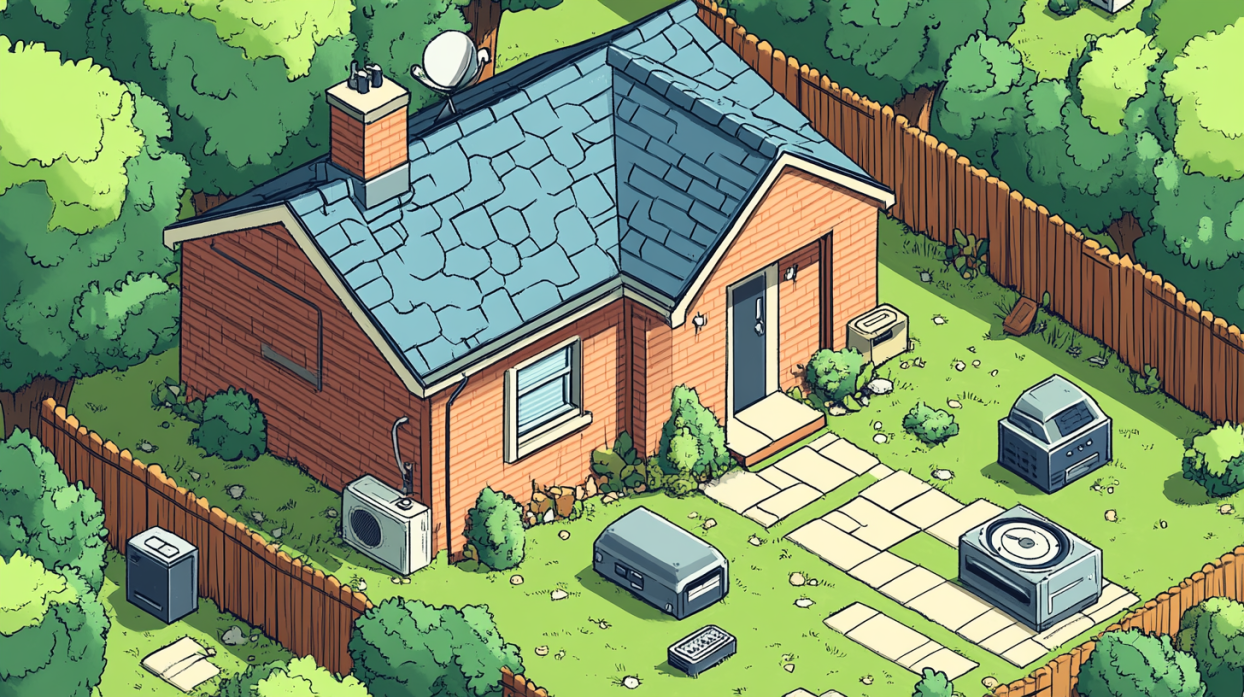
イタチの放獣場所「2キロルール」を守るべき理由
イタチを捕獲したら、自宅から2キロ以上離れた場所で放すことが重要です。この「2キロルール」には、しっかりとした理由があるんです。
まず、なぜ2キロなのでしょうか?
イタチの行動範囲が関係しています。
イタチは通常、1?2キロ圏内を活動範囲としているんです。
「え?そんなに広いの?」と驚く方もいるかもしれませんね。
2キロ以上離れた場所で放獣することで、イタチが元の場所に戻ってくる可能性を大幅に減らせるんです。
まるで、迷子になった子猫が家に帰れないようなものです。
では、具体的にどんな場所を選べばいいのでしょうか。
以下のポイントを押さえましょう。
- 森林や草原など、イタチの生息に適した自然環境
- 水源が近くにある場所
- 人家から離れた場所
- 交通量の少ない安全な場所
確かに少し手間はかかりますが、これは再侵入防止の重要な一歩なんです。
ここで注意したいのは、放獣の時間帯です。
日没前がベストです。
なぜなら、イタチは夜行性だからです。
日没前に放すことで、イタチが新しい環境に慣れる時間を与えられます。
放獣する際は、捕獲器の扉をゆっくり開け、イタチが自然に出てくるのを待ちましょう。
焦ってイタチを追い出そうとするのはNG。
ストレスを与えてしまいます。
「2キロルール」を守ることで、イタチにも優しく、自分の家も守れる。
まさに一石二鳥の方法なんです。
この方法を実践すれば、イタチ問題の解決に大きく近づけるはずです。
イタチ撃退!「臭いと音」を利用した侵入防止法
イタチの再侵入を防ぐには、「臭い」と「音」を上手に活用するのが効果的です。イタチの鋭い感覚を逆手に取る作戦なんです。
まず、臭いを使った対策から見ていきましょう。
イタチは特定の匂いが大の苦手。
この弱点を利用するんです。
- 柑橘系の香り(レモンやオレンジ)
- ハッカ油
- 木酢液
- ラベンダーの香り
「え?そんな身近なもので効果あるの?」と思うかもしれませんが、イタチにとっては強力な撃退アイテムなんです。
例えば、ハッカ油を染み込ませた布を置く方法があります。
「ひゅ?」とさわやかな香りが漂うだけで、イタチは「ここは危険!」と感じてしまうんです。
次に、音を使った対策です。
イタチは意外と音に敏感なんです。
- 高周波音(人間には聞こえない)
- 突発的な大きな音
- イタチの天敵の鳴き声(フクロウなど)
まるで、うるさい隣人がいる部屋から引っ越したくなるような感覚でしょうか。
特に効果的なのが、動体センサー付きの音響装置です。
イタチが近づいたときだけ音が鳴るので、イタチにとっては「いつ音が鳴るかわからない」という恐怖感があるんです。
ただし、注意点もあります。
臭いも音も、人間にとっても不快になる可能性があります。
使用する場所や時間帯には配慮が必要です。
「でも、効果はどのくらい続くの?」という疑問もあるでしょう。
実は、イタチは学習能力が高いんです。
そのため、定期的に臭いや音を変えると、より効果が持続します。
この「臭いと音」を組み合わせた対策で、イタチの再侵入をしっかり防ぎましょう。
家族みんなで協力して、イタチフリーの快適な暮らしを手に入れましょう!
再侵入を防ぐ!家屋の「隙間封鎖」完全ガイド
イタチの再侵入を防ぐ最も確実な方法、それが家屋の隙間封鎖です。小さな隙間も見逃さない、徹底的な封鎖作戦を立てましょう。
まず、イタチはどれくらいの隙間から侵入できるのか、知っていますか?
なんと、直径5センチの穴があれば入り込めてしまうんです。
「え?そんな小さな隙間から?」と驚く方も多いでしょう。
イタチの体は意外とやわらかく、小さな隙間でもすり抜けられるんです。
では、具体的にどんな場所を確認すればいいのでしょうか。
チェックポイントをリストアップしてみましょう。
- 屋根裏の換気口
- 外壁のひび割れ
- 配管やケーブルの通り道
- 戸袋や雨戸の隙間
- 基礎部分の隙間
懐中電灯を使って、細かい部分まで見逃さないようにしましょう。
隙間を見つけたら、すぐに封鎖します。
封鎖材料は、イタチが噛んでも破壊されにくいものを選びましょう。
例えば:
- 金属製のメッシュ
- セメント
- 発泡ウレタン
- シリコンコーキング
場所や隙間の大きさによって、適した材料を選びましょう。
例えば、小さな隙間ならシリコンコーキングで十分ですが、大きな穴には金属メッシュとセメントの組み合わせが効果的です。
特に注意が必要なのが、屋根裏の換気口です。
イタチはよくここから侵入します。
でも、ただ塞いでしまうと家の換気に問題が出てしまいます。
そこで、細かい網目の金属メッシュを取り付けるのがおすすめです。
換気はできるけど、イタチは通れない。
まさに一石二鳥ですね。
隙間封鎖は、一度やって終わりではありません。
定期的に点検し、新たな隙間ができていないかチェックすることが大切です。
家のメンテナンスと同じように、イタチ対策も継続が力なんです。
この「隙間封鎖」をしっかり行えば、イタチの再侵入リスクをグッと下げられます。
少し手間はかかりますが、安心して暮らせる家づくりの第一歩。
頑張ってやってみましょう!
意外と簡単!「小麦粉トラッキング法」でイタチの侵入経路特定
イタチの侵入経路を特定する、驚くほど簡単で効果的な方法があります。それが「小麦粉トラッキング法」です。
まるで探偵のような気分で、イタチの足跡を追跡できるんです。
この方法のポイントは、なんと普通の小麦粉を使うこと。
「え?台所にある小麦粉でいいの?」そう思う方も多いでしょう。
でも、これが意外と効果抜群なんです。
やり方は簡単です。
以下の手順で行います。
- イタチが出入りしそうな場所に小麦粉を薄く撒く
- 一晩置いておく
- 翌朝、足跡を確認する
まるで雪の上の足跡のように、はっきりと見えるんです。
「おお、これはまるで忍者の足跡追跡みたい!」なんて、わくわくしてしまうかもしれませんね。
特に効果的なのは、以下のような場所です。
- 玄関周り
- 窓際
- 換気口の近く
- 配管の周辺
「ああ、ここから入ってきていたのか!」という発見があるかもしれません。
ただし、注意点もあります。
雨の日や湿気の多い日は避けましょう。
小麦粉が固まってしまい、足跡が残りにくくなってしまいます。
また、風の強い日も避けた方が良いでしょう。
せっかく撒いた小麦粉が飛んでしまいます。
この方法の素晴らしいところは、コストがほとんどかからないこと。
特別な道具も必要ありません。
家にある小麦粉を少し分けるだけでOKです。
さらに、小麦粉は無害なので、ペットや小さなお子さんがいる家庭でも安心して使えます。
「よかった、安全な方法なんだ」と安心できますね。
この「小麦粉トラッキング法」で侵入経路を特定できれば、その後の対策もピンポイントで行えます。
効率的で効果的なイタチ対策の第一歩。
ぜひ試してみてください。
きっと、イタチとの知恵比べに勝利できるはずです!
目からウロコ!捕獲成功率を2倍にする「段階的捕獲法」
イタチの捕獲成功率を劇的に上げる秘策があります。それが「段階的捕獲法」です。
この方法を使えば、捕獲成功率が通常の2倍以上になることも。
まさに目から鱗が落ちる驚きの作戦なんです。
「段階的捕獲法」の基本は、イタチを少しずつ罠に慣れさせること。
急に罠を仕掛けるのではなく、段階を踏んでイタチの警戒心を解いていくんです。
具体的な手順は以下の通りです:
- まず、トラップを設置せずに餌だけを置く(3?4日間)
- 次に、トラップを設置するが作動させない状態で餌を置く(2?3日間)
- 最後に、トラップを作動状態にして捕獲を試みる
でも、これがイタチの警戒心を解く秘訣なんです。
この方法のポイントは、イタチの学習能力を利用していること。
イタチは賢い動物で、「ここで餌がもらえる」ということを学習します。
その学習を利用して、少しずつトラップに近づけていくわけです。
餌の選び方も重要です。
イタチの大好物を使いましょう。
例えば:
- 生の鶏肉
- 魚の切り身
- ゆで卵
また、トラップの設置場所も工夫しましょう。
イタチの通り道や、よく姿を見かける場所が最適です。
「イタチさん、ここにおいしいごはんがありますよ?」と誘っているような感覚で場所を選びます。
この方法のメリットは、イタチにストレスを与えにくいこと。
急に捕まえようとするよりも、イタチにとっても優しい方法なんです。
ただし、注意点もあります。
このただし、注意点もあります。
この方法は時間がかかるため、急を要する場合には向いていません。
また、餌を頻繁に交換する必要があるので、少し手間がかかります。
でも、その手間に見合う効果は抜群です。
通常の捕獲方法と比べて、成功率が2倍以上になることも。
「えっ、そんなに違うの?」と驚く方も多いでしょう。
この「段階的捕獲法」は、イタチの習性をよく理解した上で考案された方法です。
イタチの警戒心を解きながら、少しずつ目的を達成していく。
まるで、人間関係を築いていくようなものですね。
最後に、この方法を使う際のコツをまとめてみましょう。
- 毎日同じ時間に餌を交換する
- 周囲の環境をなるべく変えない
- 人間の匂いを最小限に抑える(手袋着用がおすすめ)
- 捕獲の最終段階では、特別に美味しい餌を用意する
「段階的捕獲法」を使えば、イタチとの知恵比べに勝利できる可能性がグンと高まります。
少し時間はかかりますが、確実にイタチを捕獲したい方にはピッタリの方法。
ぜひ、試してみてください。
きっと、驚くほどの効果を実感できるはずです!